歴代町長紹介
1888年(明治21年)に公布された町村制以後、私たちの壬生町の舵取りを担った歴代の町長をご紹介します。
旧壬生町
初代 高橋 兵右衛門 就任年月:明治22年 4月
2代 渡辺 百 就任年月:明治26年 5月
3代 大山 嘉七 就任年月:明治26年 6月
4代 沢田 興孝 就任年月:明治34年 6月
5代 石崎 戒三 就任年月:明治34年12月
6代 山口 翼 就任年月:明治36年 9月
7代 大山 嘉七 就任年月:明治40年 2月
8代 大島 正従 就任年月:大正 4年 2月
9代 大山 嘉七 就任年月:大正 7年 1月
10代 松本 茂 就任年月:大正11年 1月
11代 篠原 峯作 就任年月:大正15年 6月
12代 荒川 為右衛門 就任年月:昭和 5年 8月
13代 白石 春吉 就任年月:昭和 9年 1月
14代 佐藤 鶴七 就任年月:昭和13年 4月
15代 小田垣 健一郎 就任年月:昭和20年 6月
16代 松本 義 就任年月:昭和21年 8月

合併時
町長職務執行者
松本義

合併前も含めると、壬生町町長って今までにこんなに多くの人が就任していたんですね。
※ミバリー
広報みぶ等には何度か登場していますが、壬生の鳥「ひばり」をモチーフとし、町職員のアイデアで誕生したキャラクターです。「みぶ」と「ひばり」の言葉を組み合わせ「ミバリー」という名前になっています。
壬生町 初代町長
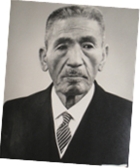
佐藤 鶴七
在任期間:昭和29年12月12日~昭和33年12月11日
昭和29年11月に稲葉村との合併後、就任。
翌年には南犬飼村が編入となり、現在の壬生町の誕生当初の多忙な町政を支えた。
壬生町 2代町長

田垣 健一郎
在任期間:昭和33年12月12日~昭和41年12月11日
昭和37年には、壬生中学校をはじめとした町内小中学校の校舎落成。昭和39年には輸出玩具団地建設が開始され、翌年には現在のおもちゃのまち駅が開設されるなど、高度経済成長時代における町の基盤の整備に尽力した。
壬生町 3代町長
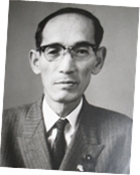
佐藤 昌次
昭和41年12月12日~昭和45年5月9日
就任中の昭和42年11月には、皇太子殿下がおもちゃ団地を視察。終末処理場の運転開始のほか、四町救急業務組合の発足、老人憩いの家の整備等、町民生活の向上を目指した各取組に尽力した。在任中の昭和45年5月に急逝。
壬生町 4代町長

佐藤 三郎
在任期間:昭和45年6月20日~昭和53年3月3日
「緑と太陽の学園都市」を将来都市像に掲げ、現在も町民の生活に大きな安心を与えている獨協医科大学を誘致。昭和48年に大学の開校、翌49年に同病院が開院となる。在任中も各施設の整備を着実に進め、昭和49年10月には総人口が3万人を突破。
壬生町 5代町長
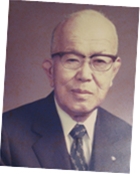
佐藤 正幸
在任期間:昭和53年4月16日~昭和57年4月15日
図書館の開館、壬生・稲葉の両中学校を統合した新生「壬生中学校」の開校など教育関係施設の整備に尽力。在任中には、国体秋季大会が開催され、壬生町では銃剣道競技が行われる。55年10月には総人口が3万5千人を突破。
壬生町 6代町長

楡井 章三
在任期間:昭和57年4月16日~平成2年4月15日
就任中の昭和60年には、現在も町の文化振興拠点である、壬生中央公民館・図書館・歴史民俗資料館を整備、また、かんぴょう生産を縁とした、滋賀県水口町(現在の甲賀市)と姉妹都市協定を結ぶなど、壬生の特長を生かした政策で実績を残した。また、各地区において住居表示を実施し、町の都市化へも貢献した。
壬生町 7代町長

清水 英世
在任期間:平成2年4月16日~平成22年4月15日
5期20年という長期間にわたり町政に尽力。就任直後の平成2年9月に、安塚地区で竜巻災害にも見舞われたが、在任中には、「緑園都市構想」を掲げ、とちぎわんぱく公園をはじめとした大規模都市公園の整備・壬生インターチェンジの開設等、現在の壬生町を形づくる都市基盤の整備において、数多くの実績を残した。
壬生町 8代町長

小菅 一弥
在任期間:平成22年4月16日~在任中
就任直後には、みぶハイウェーパークの来場者が200万人を突破。協働のまちづくりを推進していくにあたり、「壬生町民の歌」を復刻。町民1,000人を集め大合唱を開催。また、1年目に、壬生町の次の未来に向けたまちづくりのシナリオとなる「壬力UPすまいるプラン」を策定し、「人が集い・人が交流するまち」を戦略に掲げ、まちづくりを推進中。


